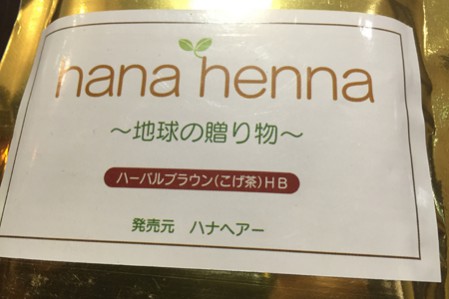
自然派思考向けのメニュー、ヘナ。天然100%の色素で白髪を染めることもできて、トリートメント効果も抜群の優れた商品メニューです。昔から人気のある商品ですから一言で「ヘナ」といっても実は様々なヘナが市場にはあります。当店で使用しているヘナも数種類。天然100%のハナヘナをはじめ、カラー剤とヘナのいいとこどりまで取り扱っています。
一般的なヘナはどちらかというとカラー剤とのいいとこ取りが多いです。なぜなら天然100%のヘナの色素は色味が薄く、一度で求める色に成る確率が少ないからです。ですからヘナとカラー剤のような染料をブレンドすることでバランスをとっているメーカーが多いのです。
ですから「100%天然のヘナをしてみたい。」と思っていても、その効果が目的に合っていないとなるとそれをする意味はありません。ですからそれぞれの特長を簡単に説明します。

カラー剤の特長
カラー剤の特長は髪を明るくすることができて、好みの色味を出しやすいというところです。その反面、髪へのダメージや色素によるアレルギーなどの問題もあります。一度では感じなくても数回重ねることでダメージは蓄積されますので、全体染めを繰り返すほどに髪のコンディションが悪くなってしまいます。
そこで少しでもダメージを軽減するために、サロン施術時に色々と工夫をしなければいけません。そこがサロンの腕の見せ所です。セルフカラーも同じですね。ただ髪を染めるということは当店ではしていません。なぜならヘアカラーを長く綺麗に楽しむためにはダメージとの兼ね合いが大切になってくるからです。
カラー剤のダメージの大きな原因はブリーチによる軟化です。ブリーチというと脱色で金髪のイメージがあるかもしれませんが、髪を明るくするということは髪の色素を取り除くことです。それはつまり髪をブリーチしているということです。
カラー剤とブリーチ剤の大きな違いは使用するアルカリ剤や金属イオン、過酸化水素によるもので、要するにカラー剤よりもブリーチの方がパワーが強いと言うとわかりやすいのですが、ブリーチのパワーを軽減することもできるので一言でブリーチの方が髪がダメージするとは言えないのですね。
天然100%ヘナの特長
ヘナの特長は白髪やカラーで退色した髪などに色素を補給しながら髪にダメージを与えない、そしてトリートメント効果があるというところです。デメリットはその色素の薄さから一度でしっかり白髪をカバーすることができないので回数を重ねたり放置時間を長くする必要がある場合があるということ、カラー剤の様に髪を明るくする力がないことです。
カラー剤の話で髪を明るくするブリーチの話をしました。髪にダメージが出る原因の1つがブリーチによる髪の軟化なんですね。ヘナはその反対の硬化なので髪がしっかりするのです。
これがヘナのメリットでもあり、デメリットにもなります。髪は硬化しすぎると軋んでギシギシになります。良くも悪くもです。髪が軋むと髪がダメージしているとイメージがありますが、髪はよくなっても軋むんですね。
でも髪が軋むの嫌じゃないですか?だからヘナを長く続けるのであればそれなりの工夫が必要です。これが当店だからできるヘナになります。ヘアカラーもヘナも長く続けるものです。だからこそメリット・デメリットをきちんと理解しないといけないのですね。
色味ですがヘナというのはオレンジにしか染まりません。髪をオレンジにしたい人は限られています。そこでデニムを染めるのに使われる「インディゴ」の青い染料を重ねる、あるいはヘナに混合することで明るいブラウン系から濃いブラウン系にすることができます。色の補色の関係ですね。
また100%ヘナといってもその生産工程において品質は異なり、それがそのまま価格に反映されているものもあるので100%天然のヘナといっても値段は様々です。劣化したヘナを再度加工しているところもあるようです。そのようなヘナは見た目では判別しにくいため、ヘナを購入する際は信用できる所から購入する様にしましょう。
ケミカルヘナの特長
ヘナのよさはわかるけど一度でしっかり染まりたい人は多いです。そこで生み出されたのがケミカルヘナです。ヘナの特長であるそのトリートメント効果は生かしつつ、染まりの欠点をカバーするためにカラー剤に使用される染料を混合し商品化しました。しかしこちらもカラー剤とヘナの調合により効果が変わります。
そしてカラー剤の染料が含まれているため、染まりが100%天然のヘナよりもいいのですが、逆に言えばカラーの染料でアレルギーの問題が残ります。ですのでケミカルヘナをする際はカラー剤でアレルギーがある場合には使用は控えたほうがいいです。
まとめ
天然100%のヘナもケミカルヘナ、カラー剤もそれぞれ特長があります。どれがいいとか悪いとかではなく、自身が求めることがそれで可能あるかどうかが一番大切です。当店ではお客様の好みの応じてヘナをセレクトしています。そしてヘナをカラーと捉えるのか、あるいはトリートメントとして捉えるかでまた発想は違ってきます。当店だとヘナはトリートメントとしての捉え方、色は入っちゃう感じですね。色としては優秀ではないので。染まりは悪いし、入ったら抜けないしじゃじゃ馬ですよ。
天然100%のヘナを理解しているからこそ、そのよさも知っています。そして天然だけの限界も同時にわかるのです。ですからご自身の目的に合った商品やメニューをセレクトしましょう。ご相談ください。
↓下記記事がよりマニアックにヘナについて書いています。
「ヘナが髪に良い」「髪が傷まない」「髪にハリコシが出る」って言うことはなんとなく認知されていますが、実際ヘナについて理解している人は少ないのでは?と言うことでヘナを少し深掘りしてヘナの良さを知ってもらう記事となります。少し難しいかも知れませんがよろしくお願いします。また、最後まで読むともれなくマニアになれます(爆)
ヘナの特徴
「ポリフェノール」という言葉は聞いたことがあるかも知れません。ヘナもポリフェノールの仲間で髪のケラチンとくっついてオレンジの色味をつけるというのがヘナの特徴となります。そして似たようなヘナの仲間が青の色味を持つインディゴです。色味や染まり具合は下記記事を参考に。
ヘナの染まる仕組み
ポリフェノールは色々なものにくっつきやすいという特徴があって、例えば緑茶に含まれるポリフェノールのカテキンによる消臭効果なら聞いたことあるかもと思いますが、匂いともくっつきやすい特徴もあります。また、金属ともその性質(いろいろなものとくっつきやすい特徴)を利用してタンニンと鉄を反応させたタンニン鉄はインクに使用されていたりします。そして、ソムリエの方ならご存知かも知れませんが、赤ワインの製造にケブラチョというタンニンを使うと鮮やかで深みのある色に、白ワインなら透明感のあるワインになるということです。
ヘナも髪にくっつきやすいのですが、そもそも酸で収斂効果があるので髪の中にはヘアカラーに比べて入りづらい(時間がかかる)。緑茶のカテキンを肌につけると毛穴を引き締めるその効果と同じようなイメージです。
メリット
抜け毛や切れ毛を予防する
ポリフェノールは簡単にいうと酸なので収斂作用があり、髪と頭皮を引き締めます。逆にダメージした髪って濡らすととろ〜んとしている。だから髪が切れやすいのです。そこにヘナすると髪が引き締まるので切れ毛予防になるということです。また、頭皮も引き締める効果があるので抜け毛の予防にもなるということです。
要はトリートメント効果と育毛効果があるってことです。
髪が染まる
説明入りますか?
ヘナはオレンジに染まりますね。これはローソンという色素が含まれているのですね。ポリフェノールっいうとわかりやすいですね。ポリフェノールは髪と結合しやすいのでヘナするとそのオレンジが中々抜けづらくなるのですね。
消臭効果で加齢臭対策に
ポリフェノールは色々なものにくっつきやすい。そう匂いに関してもです。緑茶のカテキンで消臭効果の話があったようにヘナにも消臭効果があります。加齢臭やパーマなどの残留臭対策にも期待できますね。
抗酸化作用で頭皮ケアに
色々なものとくっつきやすいと何度も出てくる話ですが、菌にもくっつきます。なので抗菌作用もあります。頭皮の肌荒れなどは菌による原因が多いので、この抗菌作用で頭皮環境改善が期待できるということです。
髪にハリコシがでる。トリートメント効果が高まる。
抜け毛や切れ毛を予防する話と同じですが、ヘナをすると収斂作用で髪がしっかりするので結果髪にハリコシがでます。ちなみに髪がヘナでしっかりするとトリートメントの効果も上がるので色々良いことづくめです。
癖がなくなる?この話は本当です。
ヘナすると癖がなくなるなんて都市伝説みたいな話ですがこの話は本当です。エイジング毛と言われる加齢が原因で癖が出るのも髪のケラチンが減って、要は髪が弱くなるのですね。で髪はハリコシがあると真っ直ぐを維持しようとするけど、ハリコシがなくなると真っ直ぐを維持できなくなります。なのでヘナするとハリコシがでるのでエイジング毛には効果的という話で、繰り返すほど髪がしっかりして癖が落ち着くという仕組みです。
また、収斂作用の話で頭皮の引き締めがありましたね。頭皮は年齢とともに重力などの影響で毛穴がたるんで癖毛やぺたんこ髪へと繋がります。ヘナすると頭皮が引き締まるので効果的ということです。
デメリット
ヘナのデメリットはメリットの逆です。
収斂作用で髪が軋む
ヘナの収斂作用でハリコシがでるので髪が軋みます。ダメージ毛などヘナするともう絡まって仕方がない。これがトリートメント効果?って。ちなみに炭酸泉などもダメージ毛なら軋みますね。意味わかってないと逆効果です。要するに髪には良い軋みと悪い軋みがあるということです。?となりますがきしみの対処法もあります。
髪が染まる
ヘナするとオレンジの色素が付いてしまうので、ブリーチ毛やヘアカラーで色味を楽見いたいって人には不向きですが、そんな方には裏技があります。
要するにヘナがすごいってことではなくてですね…
ポリフェノールがすごいということですね。ただね。じゃじゃ馬なんですよヘナ(ポリフェノール)って。癖がすごいので僕のように(汗)。なので使いこなせれば化けるということです。だからヘナを取り扱う美容室は少ないのですね。染まりづらい→工夫して染まりやすくする。髪が軋む→軋みを軽減する。色が入る→入らない工夫をする。単純な話ですが奥が深いのです。
ヘナを熟知していますのでヘナを超えたヘナ(デメリットを無くしたヘナ=メリットだらけのヘナ)もできますし、それを応用した激ヤバなトリートメントもできますよ。そうです。うちのヘナはヘナを超えたスーパーヘナです。これをメガトリートメントと組み合わせてメガトリヘナって読んでます。まぁ簡単いいうと最強のトリートメントはこれしかないと思ってます。ただここまでの話を理解できないとチンプンカンプンになってしまうので裏メニューとして一部のマニア向けという形でやれますけど興味があればチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
よくある質問
Q:白髪染めとヘナの違いは?
A: 白髪染めの種類にもよりますが、ヘナも大きな意味では白髪染めと言えます。大きな違いは色味とダメージです。一般的な白髪染めは多くの種類(ヘアカラー・ヘアマニキュア・カラートリートメントなど)があり、染料(色味)も同じように多くの種類があります。一方ヘナは1種類のみで色味もオレンジのみとなります。そしてヘナはダメージがないのも一般的な白髪染めとの違いです。
Q:ヘナカラーは何ヶ月持ちますか?
A:目安は3〜4週間に1度くらいでしょうか。頻度は通常のヘアカラーと同じです。髪は1ヶ月に平均して約1センチ伸びますので、分け目や顔まわりなど白髪が多いほど目立ちます。
Q:ヘナはどれくらいで落ちますか・
A:髪質、シャンプーなど生活スタイルによって変わりますので一概に言えません。また、染め方によっても色持ちは変わります。ヘナの色味はオレンジですのでヘナで染めたオレンジが髪に残っていれば確認できますね。
Q:ヘナで染めたあと何日でシャンプーしますか?
A:特別いつからシャンプーしないといけないということはありません。もし翌日以降などと言われるのであれば染まりが悪いという理由も考えられます。ヘナは長時間置くほど良く染まり、トリートメント効果も高まるという特徴があります。
Q:天然ヘナカラーとは何ですか?
A:一言でヘナカラーといっても内容は様々です。例えば成分100%ヘナもあれば、ヘアカラーとヘナを混合してあるメーカーもあるでしょう。 ですから天然ヘナカラーといってもヘナが100%とは限りません。サロンやメーカーによって考え方は違います。判断基準として、本当の意味での天然ヘナカラーであれば色はオレンジにしかなりません。
Q:ヘナの2度染めとは何ですか?
A:髪を染めることができるヘナはオレンジ色にしかならないため、ヘナで一度髪を染めた後にインディゴを重ねること(補色の関係)でブラウン系に染める技術です。きちんとブラウン系に染めるのであればヘナで2回染めた後にインディゴで染めた方がより良いと思います。
Q:ヘナとインディゴの違いは何ですか?
A:簡単に説明するとヘナ=オレンジ、インディゴ=ブルーです。ヘナとインディゴを混ぜて色味の調節ができます(例えばヘナ4:インディゴ6でブラウン系、ヘナ2:インディゴ8でマホガニー系など)が、白髪をしっかり染めるのであればヘナで染めた後にインディゴで染めた方が染まりは良いです。
Q:ヘナで染める時間はどのくらいですか?
A:基本は40分以上を目安としています。髪質や普段のシャンプー&トリートメントなどによって染まる時間は変わります。よく染めたり、トリートメント効果を高めるには3時間以上、また6時間おいても問題ありません。
Q:ヘナの欠点は何ですか?
A:カラーチェンジが難しくなることです。また髪が軋む場合がよくあることです。そして色がオレンジになることです。髪がしっかりするのでパーマや縮毛矯正がかかりにくくなる可能性があることもありますね。植物アレルギーが起こる可能性があることも稀ですが可能性としてあります。アレルギーはどんなものでも起こりますので。
Q:ヘナのデメリットは何ですか?
A:上記と同じになりますが、カラーチェンジが難しくなること。髪が軋む場合があること。色がオレンジになること。髪がしっかりするのでパーマや縮毛矯正がかかりにくくなる可能性があること。植物アレルギーが起こる可能性があることなどです。
Q:ヘナ染めの効果は何ですか?
A:最大の効果は髪がダメージすることなく染められることと、頭皮と髪を強化するトリートメント効果です。
Q:ヘナは何回染めれば効果が感じますか?
A:染め方にもよりますが1回でも十分効果は感じられると思います。育毛効果・癖を抑える効果などは回数を重ねないと感じにくいかもしれません。あまり時間を空けずに月に1度ヘナをして3回くらいヘナをするとその良さを感じてもらえると思います。
Q:ヘナショックは何回でなおりますか?
A:やり方次第です。トリートメントと併用すればヘナショックは起きにくくなります。一般的にダメージの強い髪ほどヘナショックは起こります。4〜5回と回数を繰り返せばなくなるというよりも気にならなくなるといった方がいいかもしれません。なぜならヘナには収斂作用がありますのでその都度収斂は起こるからです。基本的に酸系を使用すると髪は収斂しますので軋みます。炭酸でも髪が軋む場合があるのと同じですね。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。













この記事へのコメントはありません。